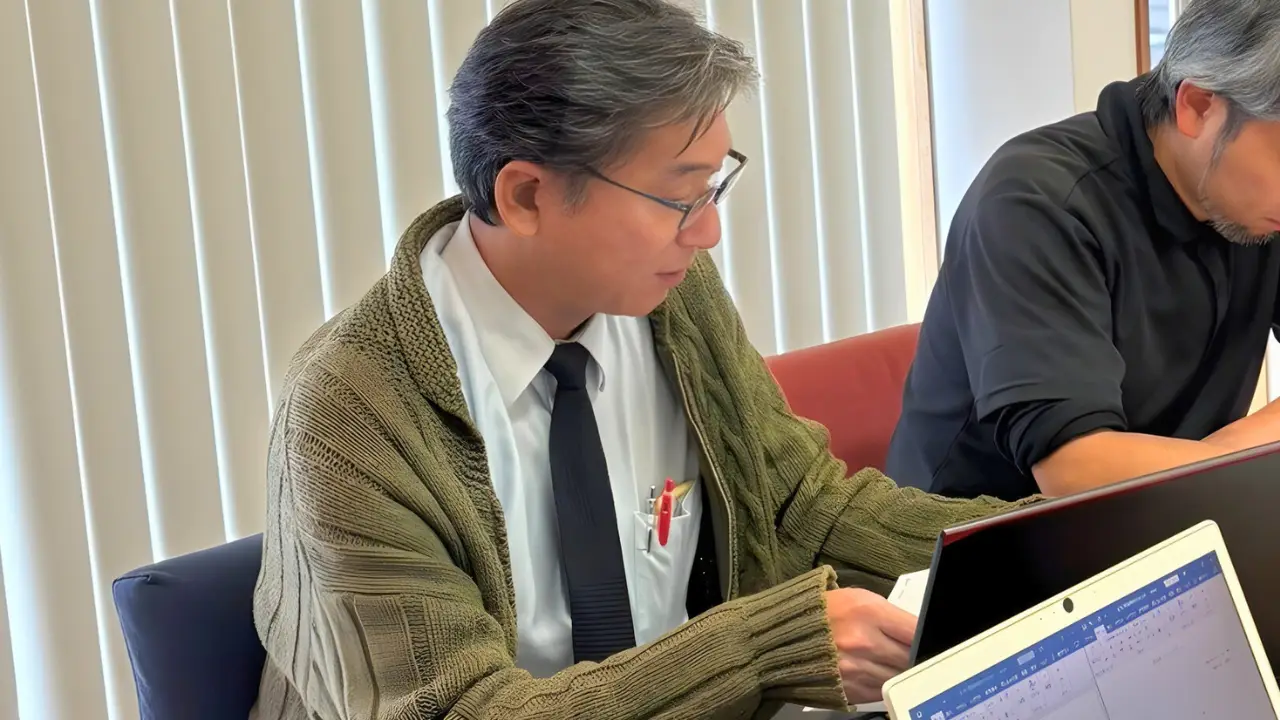”信頼”を大切にした10年が証明する未来会計の力——税理士法人MIRAI 伊藤秀太朗

目次
秋田県秋田市の税理士法人MIRAI(兼、株式会社MIRAIサポート)で、未来会計プランナーとして企業支援を行う伊藤さん。数字の先にある経営の本質に寄り添い、現場の声を引き出しながら利益改善を実現してきました。「将軍の日」やMAS監査などを通じて、経営者が本気で未来と向き合う時間をつくる——そんな支援が、企業にどんな変化をもたらすのか。その実践から、未来会計の真価が見えてきます。
税理士法人MIRAI
伊藤秀太朗秋田県秋田市の税理士法人MIRAI(兼、株式会社MIRAIサポート)で未来会計プランナーとして企業の経営支援を行う。商業高校卒業後、建設会社での約7年間の経理業務を経て、現在の税理士法人MIRAI/株式会社MIRAIサポートの前身である澤田石晶税理士事務所へ転職。以来、数字の先にある経営の本質に寄り添い、現場の声を引き出しながら利益改善を実現してきた。「将軍の日」やMAS監査を通じた支援は、多くの企業に変化をもたらしている。令和7年11月1日より、株式会社MIRAIサポートの代表取締役に就任。 |
これまでのキャリア
Qまず、伊藤さんのこれまでのキャリアのことをお伺いしたいと思います。会計業界に入った経緯を教えていただけますか?
商業高校卒業後に、Aクラスの公共工事を請け負っている秋田市の建設会社に経理担当として入社しました。そこで約7年間、経理業務に携わっていました。次第に「コンクリートではなく、人間を大事にする」という社会背景の流れがあり、建設業界が厳しくなってきた中、将来に不安を感じ、また新しいチャレンジも求めて転職を考えるようになります。
そういった中で転職したのが、現在の税理士法人MIRAI/株式会社MIRAIサポートの前身にあたる澤田石晶税理士事務所という個人の会計事務所でした。自分の腕試しという気持ちと最後まで勤められる価値のある職場だといいなという期待感があったのを覚えています。当時20代中盤くらいの時期だったと思います。
Q会計事務所でのやりがいについてですが、入社当時はどんなことを期待されていましたか?
人と会ってコミュニケーションを取ることが好きなため、「自分に合っている仕事に違いない」と期待していました。求人票に掲載されていた情報から色んな会社の社長さんにお会いして、頻繁にコミュニケーションを取る仕事のイメージがありました。
実際に会計事務所で働き始めてからは、それまで経理担当者として内勤で働いていたときと比べて、毎日違う人とお会いして話すことはとても新鮮でした。
会計事務所に入社してからは顧問契約を結んでいる企業に月に1回訪問し、現金出納帳や請求書、領収書、そこから出来上がった会計帳簿を税法と照らし合わせて正しいかチェックを行いました。最初の1ヶ月は徹底したOJTだったので、毎日業務に対するプレッシャーの連続で、やりがいを考える暇がなかったことを覚えています。
Qいきなり会計事務所の現場に入られてスキル的に足りない部分も多かったと思いますが、忙しい日々の中でどのようにして足りない部分を補ってきたのでしょうか?
前任の先輩は1ヶ月で退社されたのですが、私だけでは分からない点が多くありました。そのため退職された後も正直半年ぐらいは毎日電話でわからないことを聞いていました。前任の先輩は15社の顧問先を担当していて、社長から信頼されていました。
「先輩が築かれた信頼をそのまま引き継げるのか」「どのように信頼を繋いでいけばいいのか」とそればかり考えていました。
業務上のスキルも大切ですが、それ以上に必要なものはお客様からの信頼だと思います。士業の仕事に比べて成果物だけだと他の事務所とあまり違いがないだけに、余計に信頼関係が大切になってきます。
未来会計との出会い
Q会計事務所職員という肩書の他に、未来会計プランナーとして未来会計の仕事にも携わっていくことになると思いますが、未来会計プランナーの仕事に携わるようになったきっかけを教えていただけますか?
約10年前、当時所長だった澤田石が未来会計に関するセミナーを受講しました。
澤田石は税理士業界の未来に対して危機感を持っていました。従来の税務会計に代表される過去会計だけでは将来立ち行かなくなる。これからは未来会計が重要だと事務所に戻って熱を持って話す澤田石の話に職員も深く考えるようになり、未来会計を事務所全体で取り組むようになりました。
私自身も一般の事業会社で働いていた経験もあり、経営計画から始まる未来会計の考え方を何の違和感もなくスムーズに取り入れられました。今までのお客様との関わりとはまた全く違う形で、顧客満足を創出できる新たなフィービジネスの可能性にワクワクしました。
Q.10年間の未来会計プランナーの活動の中で、具体的にどのような取り組みを進めてこられたのでしょうか。
未来会計の取り組みを始めた当初は関東を中心に未来会計業務実践に繋がる研修を受講し、未来会計の全体像をつかむことができました。また約10年前に秋田の中小企業家同友会の『経営指針を作る会』があり、当時の売上1億円を5年で1.5倍にしようという経営計画を自分たちでも立ててその計画に基づいて動き始めました。それまでは経営計画を立てたことはなかったのですが、お客様の見本になるためにも経営計画をお客様だけでなく事務所にも導入しました。
MAP経営の横尾さんにコンサルに入っていただき、自社でPDCAを回す活動を始めました。横尾さんから未来会計を提供いただいたことで、会議の進行方法やPDCAの回し方、みんなのモチベーションをコントロールする術などサービスのイメージがついてきました。「横尾さんにコンサルいただいたことを顧問先に提供したら良いのか!」と気づきが得られたのは大きな収穫でした。
社員の意見発信の場を作り、600万円ものコスト削減を実現した支援事例
Q.その後お客様をサポートする段階へ入ると思いますが、印象に残っている会社様やサポート後の嬉しかった変化など、実績と合わせてご紹介いただけますか?
会議の場を設けることで現場で働く方の意見を拾うことができ、経常利益が上がったお客様がいらっしゃいました。そこは私の未来会計の契約先第1号で、8年くらい契約いただいていたお客様です。年商3億円くらいの会社で自動車の部品を全国に発送する仕事をされていて、仲良くさせていただいている社長さんでした。
支援内容として、社長含めて6名にご参加いただき会議を毎月しました。最初は会議を開いても社長のトップダウン色が強く、活発な意見が飛び交う雰囲気ではなかったという記憶があります。このままでは顧問料に見合うサービスが提供できないという、ひどいプレッシャーがかかりました。
そこで会議に参加するメンバーを変えて、当時課長で現在は部長を務められている方にご参加いただきました。その方に未来会計や会議の目的を最初から説明すると、その方からコスト削減について改善案が出てきました。その改善案は「商品のサイズにあっていない段ボールで運ぶことをやめませんか?」というものです。
当時、運送会社との契約で使用している段ボールの大きさは4つか5つくらいしか種類がありませんでした。そのことにより、本来500円くらいで送れる商品を1,200円くらいで送っており、当時課長は無駄だなと思っていたそうです。そういった意見を吸い上げたり、発言する仕組みがなく、今までなんとなく悪習慣として根付いていたことを誰も指摘することがありませんでした。その解決策は「契約の運送会社と交渉してダンボールのサイズ展開を増やしてもらうだけで、月間で最低50万円以上のコスト削減できる」というものでした。
改善案通りに運送会社へ話を通すと、結果的に年間で600万円ものコスト削減が実現しました。売上に全く関係ない変動費なので、売上を変えずに経常利益を上げられたため、社長もとても喜んでました。経営改善のヒントは社長だけでなく、現場で働いている人たちが持っていることが多くあります。中小零細企業では意見やアイデアを吸い上げる機会がないだけで、案外良いアイデアが埋もれているかもしれないと私自身も気づきがありました。
MAS監査による支援事例ー経営理念を見つめなおすー
Q経営者自身の変化によって良い方向に経営が向かった、などのエピソードはありますか?
以前「将軍の日(中期五ヵ年経営計画立案セミナー)」にご参加いただき、月額10万円でMAS監査のご契約をいただいたお客様の事例をご紹介します。まず、初回のMAS監査では「将軍の日」で作成いただいた5ヶ年の年度計画から初年度にあたる1年目を単年度計画で月次の数値計画に落とし込みます。その数値計画を達成するために、何が必要でどういう行動をしないといけないかを明確にしました。
その会社さんは『自他共栄』を経営理念とされていて、自社だけでなく取引先の会社さんにも幸せになってほしいという思いを理念として掲げられています。MAS監査を導入する直前の第2期決算では3,600万円の赤字を計上してしまい、このままではまずいということで、「将軍の日」に参加され改めて外部の専門家による経営支援の必要性を社長自らが強く感じ、MAS監査の契約を結んでいただきました。
これまでは取引先さんや外注先、材料調達先の会社さんに対していっさい値引き交渉をせず、相見積もりをとらず、先方から言われた金額で取引が行われていました。また原価管理も全然できていなくて、いわゆる財務はどんぶり勘定で限界利益率が10%もない状態でした。最低でも22%まで限界利益率を引き上げないと黒字にならないことを単年度計画を立てる際にお伝えしました。
それを社長にお伝えした際に、社長は『自他共栄』の意味を履き違えていた、これからは自分たちが黒字にならないといけないし、取引先業者さんにも色々手伝ってもらわないといけない、そのために適正や取引交渉を行っていくことを意思決定いただきました。そうすることで限界利益率22%以上を目指せると言われてました。その会社さんは工事の受注は今年度確定しているものが多くあり、売上以上に利益率に課題がありました。利益率が改善することで1年で当期利益が3,600万円の赤字から、400万円の黒字という4,000万円の利益改善を出す計画を一緒に作ることができました。
MAS監査をはじめてちょうど一年が経過し、先日確定した第3期の決算では結果的に当期利益が1,800万円と大幅な黒字決算となり、社長をはじめ会社の皆さん全員でその成果を喜び合いました。
経営者の方へ向けてメッセージ
Q中小企業の経営者に向けて、未来会計の価値やどのように自分たちを使ってもらいたいかなど、メッセージをお願いします。
まずは自社で開催している「将軍の日」というイベントにぜひ、参加いただきたいです。将軍の日のプログラムがとてもよく出来ていて、中小企業の社長にとって丸一日自社の経営に向きあっていただくことで「将軍の日に来てよかった」「経営計画を作ってよかった」と言っていただける一日になる自信があります。
Q未来会計プランナーが担当につくメリット、価値はいかがですか?
第三者を入れないで、自前で会議をして結果を出すのは意外と難しいです。私たちも当時MAP経営の横尾さんに入っていただかなければ、自分だけではとても同じような結果は出せていなかったと思います。知識として勉強して知っていることとできること、できることと成果を出せることもまた違うと思います。そこが経営の難しさでもあると思いますし、だからこそ第三者のサポーターとしての未来会計プランナーの価値があるのではないかと思います。
会計事務所で働く方へ伝えたい「未来会計プランナーの仕事としての魅力」とは
Q最後に会計事務所でこれから働く、または会計事務所の中でどうやってキャリアを描いていこうかと悩んでいる方へ向けて、未来会計プランナーとして活躍することのやりがいなど、応援メッセージをお願いします。
未来会計は過去会計のような価格競争に一切左右されず、自分自身のスキルを磨いて付加価値を高めれば高めるほど顧問先に貢献出来て報酬もいただける、無限の可能性がある仕事だと思います。
未来会計サービスで良い成果を継続的に出し続けることができれば、関わる顧問先の利益にも当然繋がります。会計事務所業界として考えたらAIが今後普及したとしても、コンサルティング領域はAIが真似の出来ない領域だと思います。事業で考えると私がいる秋田県で税務顧問報酬で月額10万円をいただくのは至難の業です。
しかし未来会計だと月額10万円にとどまらず、月額15万円や20万円の提供価値を届けられる可能性があります。すごくやりがいがあって、顧問先にとって自分自身の存在価値を感じられるのも未来会計プランナーの魅力です。まずはやってみて、自分に合うのか見極めていただくと良いと思います。